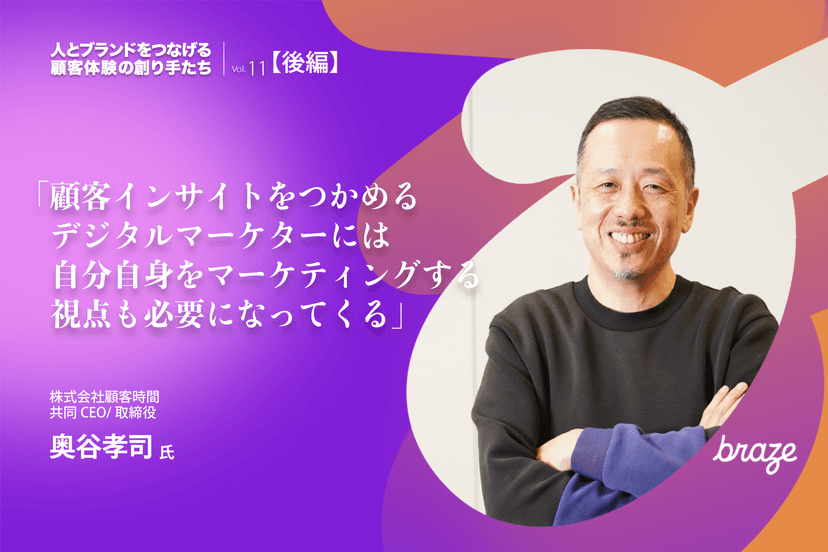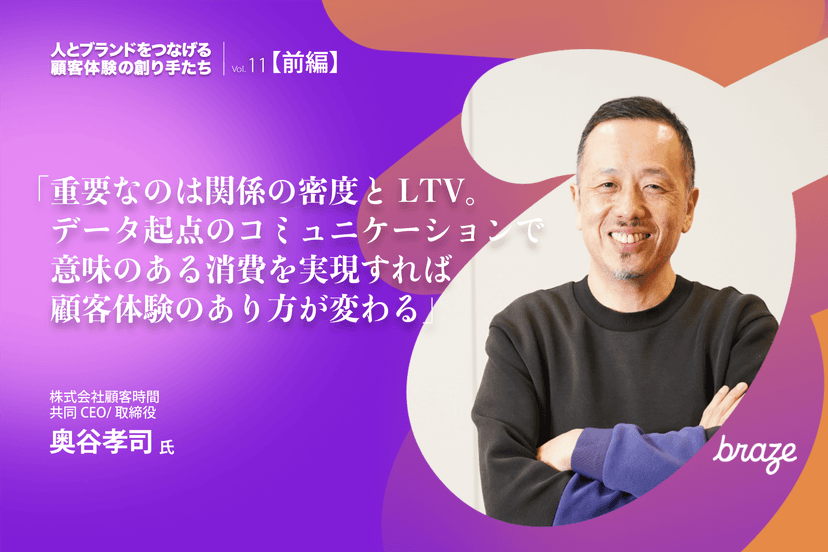顧客体験の向上のための「OMO戦略」とは?メリットや成功させるポイントを紹介
公開 2023年6月20日/更新 2023年8月04日/13 分で確認


Team Braze
顧客接点の多様化やコモディティ化の脅威が語られる中、注目を集めているマーケティング手法「OMO戦略」。その理解は、企業の長期的な成長に欠かせない「顧客体験の向上」に結びつきます。
この記事では、OMO戦略の概要と重要性、メリットとデメリット、成功させるためのポイントをご紹介します。
1. OMO戦略とは
OMO戦略とは、オンライン(インターネット)とオフライン(実店舗)の融合により顧客体験を向上させるマーケティング戦略です。その特徴を理解するためには、まずOMOとは何かを知る必要があります。
1.1. OMOとは
OMOは「Online Merges with Offline(オンライン マージズ ウィズ オフライン)」の略称です。日本語では「オンラインとオフラインの融合」と訳され、顧客がインターネットと実店舗の違いを感じないほどのシームレスなサービスを提供し、顧客体験を向上させていく考え方を意味します。
OMOの詳細や導入事例は、以下の記事もあわせてご確認ください。OMOの意味とは?オムニチャネルとの違いやメリット、導入事例について紹介
1.2. マーケティング手法である「OMO戦略」
OMO戦略とは、上記のOMOの考え方により進められる企業戦略やマーケティング手法を指します。例えば「ネットショップで注文や決済を事前に済ませ、実店舗では品物を受け取るのみ」といったサービスを考案・実践していくのがOMO戦略です。
すなわち、OMOはネットと実店舗の融合そのものを意味しており、それをビジネスに落とし込むための具体的な方策がOMO戦略となります。
1.3. オムニチャネルやO2Oマーケティングとの違い
OMO戦略とよく似た言葉に「オムニチャネル」と「O2Oマーケティング」があります。
オムニチャネルは、顧客と自社製品の接点(チャネル)の数を増やし、あらゆる機会を逃さずアプローチしようとする考え方です。OMO戦略がオンラインとオフラインのチャネルの融合を目指すのに対し、オムニチャネルは接点数の増加を目標とする点に違いがあります。
O2Oマーケティングは、メルマガやインフルエンサーによるSNSでの宣伝など、オンラインで集客を行い実店舗で購買をさせる手法です。オンラインが集客装置、実店舗が購入場所と、両者の役割が明確に分かれている点でOMO戦略と異なります。
あらためて、ここまでの各用語の概要を以下にまとめます。
用語名
概要
OMO
オンライン(インターネット)とオフライン(実店舗)の統合により顧客体験を向上させる考え方
OMO戦略
OMOの考え方により進められる企業戦略やマーケティング手法
オムニチャネル
顧客と自社製品の接点(チャネル)の数を増やし、あらゆる機会を逃さずアプローチしようとする考え方。OMOのような接点の統合ではなく、接点数を増やすことを目指す
O2Oマーケティング
オンラインで集客を行い実店舗で購買をさせる手法。集客はオンライン、購入は実店舗と、両者の役割が明確に分かれている点でOMOとは異なる
2. OMO戦略の重要性
近年OMO戦略の重要性が増している理由には、主に以下の3点が挙げられます。
- 顧客接点の多様化スマートフォンの浸透によりインターネットが身近なものとなり、気になることはまずSNSで検索する人も現れるなど、オンラインによる顧客接点の必要性が高まりつつある。
- 利便性の向上ECサイトが隆盛を極める中で配送の高速化も進み、夜間に注文した商品が翌日に届くことも当たり前に。オンラインでの購買行動が一昔前とは比較にならないほど当然のものとして受け入れられている。
- コモディティ化の進行IT技術の進展により、新商品に対する後発の類似製品が素早く登場するように。差別化のため、商品の技術面以外の価値(手軽に購入できる、アフターフォローが丁寧など)を高める必要性が増している。
OMO戦略を進める目的は、上記のような現代のビジネス課題に対応できる形に企業活動を最適化していくことにあります。
3. OMO戦略のメリット
では、OMO戦略によって企業はどのようなメリットを享受できるのでしょうか。
3.1. 顧客のニーズを把握できる
OMO戦略では、オンラインとオフラインの両側面から顧客の行動データを収集できる枠組みを作ります。それにより、従来よりも大量のデータを、これまでよりも手軽な形で収集できるようになります。収集された大量のデータを分析することにより、高精度な顧客ニーズの把握が可能となります。
3.2. 機会損失が防げる
OMO戦略の実践により顧客が自社製品を購入しやすい環境を整えることは、販売機会の損失防止に結びつきます。例えば、ECサイトで品切れの場合に「近場の実店舗に在庫がある」とマップ付きで顧客に知らせることで、購買熱が冷める前の訪問を期待できます。
3.3. 質の高い顧客体験が提供できる
オンラインとオフラインの境目をなくした販売施策は、店舗の近くを訪れたタイミングでスマートフォンに割引クーポンが届くなど、顧客に新時代を思わせるユニークな体験を提供できます。ニーズを踏まえた施策の実行により、OMO戦略なしでは実現し得ない喜びを顧客に満喫してもらえます。
4. OMO戦略のデメリット
OMO戦略は現代に必須ともいうべきマーケティング手法ですが、コストと成果が出るまでの時間には注意が必要です。
OMO戦略の実践には、ITツールや機材の導入など、相応の初期費用がかかります。保守費用や月額利用料といった運用コストも求められるため、実行前には十分な予算を用意しなければなりません。
さらに、OMO戦略は実践直後に100%の効果が得られるものではなく、収集データを元にした新施策の検討を繰り返して初めて真価を発揮します。予算と時間的猶予を確保できるだけの企業体力があるうちに推進することが大切です。
5. OMO戦略を成功させるためのポイント

続いて、OMO戦略を成功させるためのポイントを見ていきましょう。
5.1. ペルソナ(顧客像)を把握・理解する
OMO戦略は、単にオンラインとオフラインの境目をなくすだけでなく、顧客体験の向上までを目指しています。それには、収集したデータを分析して、これまで以上に顧客像を明確にしていくことが欠かせません。ペルソナが明確になれば、一人ひとりに適した体験を提供できるようになり、やがては「まるで私のためにあるようなサービスだ」と感じるファンを数多く生み出せます。
5.2. チャネルやタッチポイントごとに対策を考える
顧客と自社製品の接点(チャネルやタッチポイント)を網羅し、それぞれに応じた施策を考えることも重要です。例えば、SNSなら外部インフルエンサーとの契約や自社オリジナルキャラクターの運用、実店舗ではQRコードの読み取りでその場でECサイトからも購入できるようにするなど、接点によって顧客体験の向上に役立つ対策は異なります。
5.3. 収集したデータを一元管理する
ペルソナの把握と顧客接点別の対策を実現するためには、データの有効活用が欠かせません。そのためには、収集したデータの一元管理を進めるなど、データ分析・活用に取り組みやすい環境自体を整える必要があります。データを集めただけで満足してしまうことは、OMO戦略でよくある失敗例の一つです。
6. OMO戦略に取り組むための流れ
続いて、OMO戦略を成功させるための具体的な流れをご紹介します。
6.1. タッチポイントの整理や顧客体験を把握する
まず行うべきは、顧客接点と顧客体験の網羅的な把握です。前述の通り、OMO戦略の成功にはペルソナ像の明確化やチャネル別の対策の考案が欠かせません。自社製品との出会い、購買を決定するまでの情報収集、購入方法、実際の利用シーンに至るまでの顧客行動を理解しましょう。把握の手法としては、顧客へのアンケートが考えられます。
6.2. 現状を振り返り課題を洗い出す
続いて、現時点で把握したタッチポイントや顧客体験を元に、顧客が不満を抱きそうな過程(現状の課題)を洗い出します。例えば、「ECサイトの品切れが多い」「商品の説明を受けたいのに店頭での待ち時間が長く、諦めて帰る顧客がいる」「購入前に商品を手に取り触れる機会がない」などです。
6.3. 顧客体験を向上させるための流れを設計する
課題の洗い出しの後は、生じているであろう不満を解消できる施策、すなわち顧客体験を向上させるための流れを設計します。前述の例であれば、「品切れ時に近隣店舗の在庫情報を表示する」「ビデオ通話など店頭以外の場所でも商品説明を受けられるようにする」「実店舗に試用スペースを設け、使用感を確かめられるようにする」などが挙げられます。
6.4. ツールやシステムの導入を検討する
顧客体験改善の流れを設計できたら、実行に必要なツールやシステムを検討します。ECサイトの品切れの例であれば「リアルタイムで店頭の在庫を把握・表示できるWebシステム」、店頭待ち時間の例なら「低遅延のビデオ通話ツール」などが必要でしょう。実店舗に試用スペースを設ける例のように、オフラインでのアクションを検討すべきケースもあります。
7. OMO戦略を成功させるにはBrazeの活用を
OMO戦略の成功には、データの収集と分析が必要不可欠です。オンライン・オフラインどちらのアクションを進める際でも、その重要性は変わりません。しかし、顧客データの収集や分析の方法が思い付かない企業も多いでしょう。
解決策としてご検討いただきたいのが、マーケティング担当者向けのカスタマーエンゲージメントプラットフォーム「Braze」です。
7.1. Brazeの活用メリット
Brazeはリアルタイムで顧客の行動と嗜好を分析し、最適な形でのプロモーションを実現するツールです。複数チャネルの情報を一元管理でき、OMO戦略の実施に必須である現状課題の把握をサポートします。
また、希望条件を元に顧客へ多様なアプローチができるのも特徴です。「ECサイトを訪問した人に店頭で使えるクーポンを配布する」「実店舗のセール情報をスマートフォンへの通知で送信する」といった、オンラインとオフラインの垣根を越えたアクションを可能にします。
7.2. OMOの事例紹介
ここでは、Brazeを導入したOMOへの取り組み事例を2つご紹介します。
7.2.1. 事例1
年間4,000万人以上の顧客が来店するオーストラリア最大のカフェ「The Coffee Club」。世界9ヵ国に進出するなどグローバル展開を進める同企業では、自社の顧客情報をまとめて管理できておらず、実店舗型ビジネスにありがちなデジタル化の遅れに悩まされていました。
しかし、Brazeの導入により、店頭のPOSシステムと連携したスマートフォン(アプリ)からのクーポン提供など、顧客情報の有効活用を進めた結果、ロイヤルティプログラムの会員からの売上を35%増加させることに成功しました。
The Coffee Club、クロスチャネルアプローチでロイヤルティ会員の売上が35%増加、アプリ評価も向上
7.2.2. 事例2
株式会社アイスタイルは、コスメ・美容に関する総合サービス「@cosme」を提供する企業です。 ECサイトの「@cosme SHOPPING」、実店舗のショップ「@cosme STORE」を運営するなど手広く活動しており、その豊富な顧客接点のハブとして自社アプリを提供していました。しかし、顧客一人ひとりに合わせたアプローチは難しく、同アプリ内では画一的な宣伝しかできていないのが実情でした。
そこで、解決策としてBrazeを導入しました。細かな条件のもと、顧客それぞれに適した情報を提供するようアプリを改善した結果、わずか3ヵ月でMAU(Monthly Active Users:月間当たりのアクティブユーザー数)が1.5倍にまで上昇しています。
Braze導入3ヶ月で昨対MAU1.5倍!@cosmeの多様な入口をアプリで繋ぐアイスタイルの挑戦
8. まとめ
この記事では、OMO戦略について、その特徴や重要性、メリットとデメリット、成功までのポイントと流れをご紹介しました。
インターネットと実店舗の融合を進めるOMO戦略の実践は、従来とは異なる形による顧客体験の向上を生み出します。しかし、十分な成果を得るためには相応の時間が必要であり、企業には速やかな取り組みが求められています。
カスタマーエンゲージメントプラットフォーム「Braze」サービス詳細の確認はこちら>https://www.braze.co.jp/
デモ版利用などのお問い合わせについてはこちら>https://www.braze.co.jp/contact
関連タグ
Be Absolutely Engaging.™
Brazeの最新情報を定期的にお届け