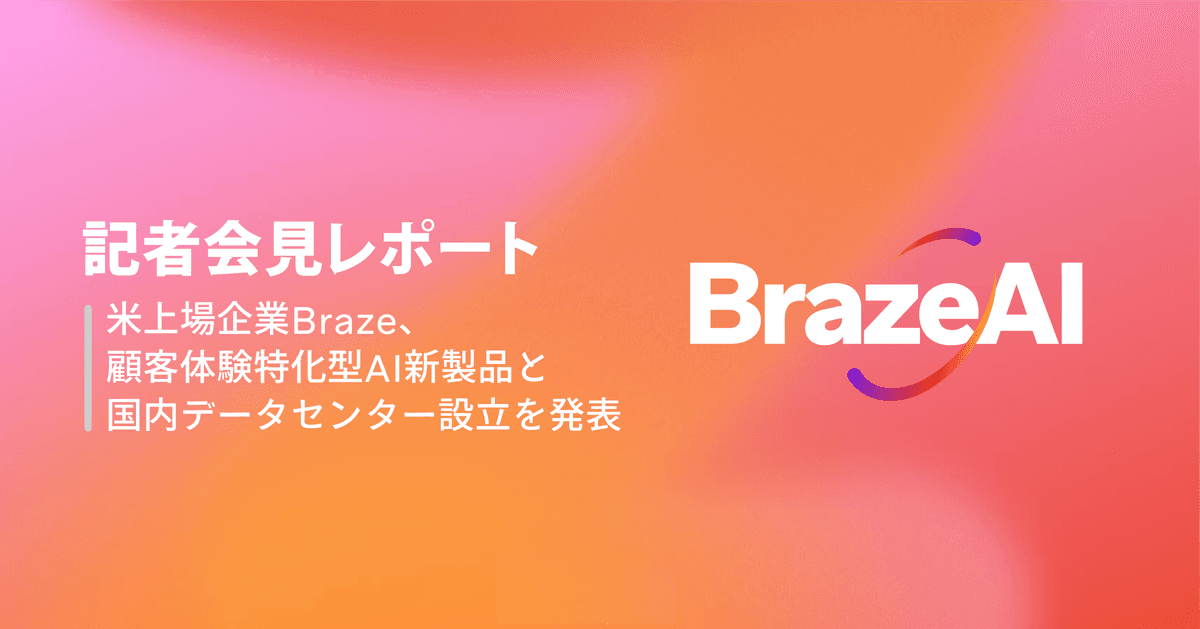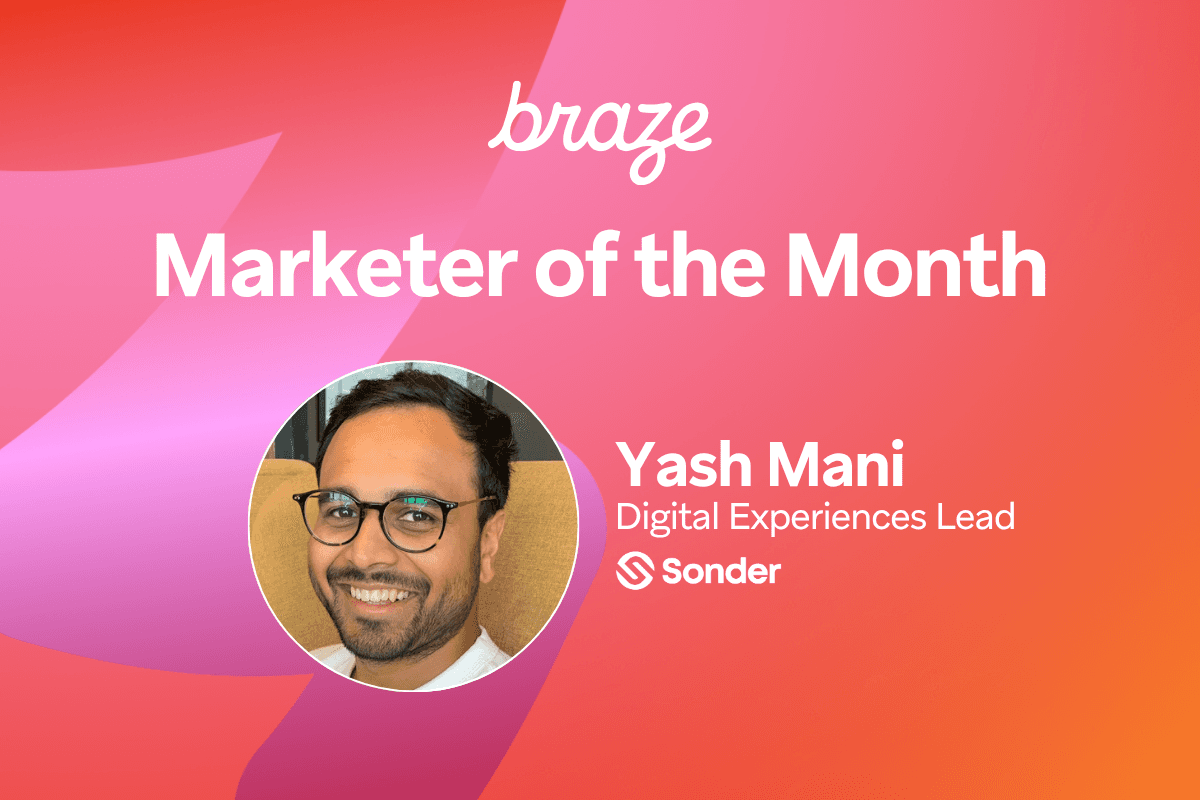オムニチャネルとは?必要性や混同されやすい用語・導入メリットについて
公開 2025年9月18日/更新 2025年9月18日/13 分で確認


Team Braze
実店舗、ECサイト、SNSなどのチャネルによって商品価格や在庫が異なることが原因で顧客からのクレームが生じた経験はありませんか?このような苦情を避け、ブランドの一貫性を高めるマーケティング戦略が、オムニチャネルです。
この記事では、オムニチャネルの意味や重要視される背景、関連用語との違い、メリットやポイント、導入手順などをご紹介します。
1.オムニチャネルとは?
オムニチャネルとは、さまざまな顧客接点(チャネル)を統合的に連携させて販売を進めるマーケティング戦略です。名前のオムニ(Omni)は「すべての」を意味しており、顧客がチャネルの違いを意識せずに自由な形で商品を購入できることを目指します。
例えば、店舗で商品が品切れしていても、その場で陳列棚のQRコードを読み取りECサイトで注文し、支払いは店舗のレジで完了。自宅と店舗のどちらで受け取るかを選べるなど、顧客が好きな形で購入や受け取りができる形が「オムニチャネル」と呼ばれます。
ここでいうチャネルとは、主に以下を指します。
- 実店舗
- SNS
- 自社アプリ
- 動画サイト
- ECサイト
- メール
- 各種広告(チラシ、バナー広告などオンラインオフライン問わず) など
とある調査によれば、オムニチャネルコマースの市場規模は今後も拡大すると予想されており、近年大きな注目を集めています。
2.オムニチャネルが重要視されるようになった背景
オムニチャネルが重要視される背景には、以下のような理由があります。
2.1.顧客接点の多様化
スマートフォンが浸透し、顧客と自社の出会いの形が多様化したため、SNSや動画サイトのような従来とは異なる接点からもスムーズに購入してもらう必要性が高まっています。
2.2.競合製品との差別化
市場のグローバル化や生産技術の進化により、後発品が早く登場するようになったため、スムーズに購入できるという付加価値の魅力が増してきています。
2.3.新規顧客獲得の難化
市場に数え切れないほどの製品が登場するなか、新規顧客獲得の難易度が増しています。そのため、オムニチャネルで特別な体験を提供し、既存顧客からの売り上げ拡大を目指すことが、その解決策の一つとなっています。
3.混同されやすい用語との違い
オムニチャネルには混同されやすい用語が存在します。それぞれの意味やメリット・デメリットを見ていきましょう。
3.1.シングルチャネル
シングルチャネルとは、顧客との接点が一つしかない状態を指します。実店舗だけ、ECサイトだけのような形です。
【メリット】
- 運用コストがあまりかからない
- チャネルが一つしかないため管理が容易
【デメリット】
- 購買機会を逃す可能性が高い
(例:実店舗で手に取ってみたかった)
- 不便だとみなされ顧客満足度が下がる恐れがある
3.2.マルチチャネル
マルチチャネルとは、複数の独立したチャネルがある状態のことです。実店舗、ECサイト、自社サイト、SNSなどいくつかの顧客接点を持っているものの、それぞれの連携はされていません。
【メリット】
- シングルチャネルよりも顧客を取りこぼしにくい
- ある程度のブランド認知度向上も見込める
【デメリット】
- 在庫管理が複雑になりやすい
- ブランドイメージがあいまいになりやすい
(例:実店舗は高級路線だがECサイトでは頻繁にセールがある)
3.3.クロスチャネル
クロスチャネルとは、複数のチャネルがあり、ある程度の連携も行われている状態です。オムニチャネルの前段階にあたり、ECサイトで購入した商品の受け取りや返品を実店舗で対応する、といった仕組みが代表例です。
【メリット】
- オムニチャネルよりも気軽にはじめやすい
- 顧客に一定の利便性を届けられる
【デメリット】
- 顧客体験のつぎはぎ感が生じやすい
(例:ECサイトで購入した商品は店舗で受け取れるが、カタログ注文の商品は自宅受け取りのみ)
- オムニチャネルほどの体験を提供できず、取り組みが中途半端になる恐れがある(※費用とリターンが見合わないことがある)
クロスチャネルについては以下の記事でより詳しく解説しています。
>>顧客接点の多様化に対応したクロスチャネルについて-オムニチャネルとの違い
3.4.O2O
O2O(Online to Offline)とは、オンラインでの集客施策をオフラインの購買行動につなげることを意味します。最終的な購買の場が必ずオフラインである点がオムニチャネルとの最大の違いです。
【メリット】
- 購買の場をオフラインに限定しているため効果測定しやすい
- 実店舗のみを持つシングルチャネルから移行しやすい
【デメリット】
- 地理的な制約がある(※実店舗の商圏外の顧客は購買できない)
- 客単価の向上が難しい(※割引系の施策がメインとなりやすい)
O2Oについては以下の記事でより詳しく解説しています。
>>O2Oの意味とは?OMOとの違いや実施メリット、成功事例について徹底解説
3.5.OMO
OMO(Online Merges with Offline)とは、オンラインとオフラインの融合によって顧客体験(CX)の向上を目指すマーケティング手法です。
複数の接点を統合してアプローチを行うオムニチャネルに近い概念ですが、OMOは顧客体験の向上を主目的とし、オムニチャネルは顧客接点の増加(販売機会の取り逃しの防止)をより重視していると分けられることもあります。
【メリット】
- オムニチャネルと同様、顧客に新時代の体験を提供できる
- 顧客視点での改善を進められる
【デメリット】
- 導入コストが高額になりやすい
(例:チャネル別の顧客情報をリアルタイムに連携できるツールの導入)
- PDCAサイクルを回すなど長期的な視点が必要
OMOについては以下の記事でより詳しく解説しています。
>>OMOとは?小売業界での重要性やオムニチャネルとの違い、導入事例についても紹介
4.オムニチャネル化を進めることで得られるメリット

では、オムニチャネルの推進することで得られるメリットを見ていきましょう。
4.1.販売機会の損失を防ぐことができる
オムニチャネルにより複数の顧客接点を有効活用することは、販売機会の損失防止に繋がります。
例えば店舗で品切れが起こったとき、本来であればそのまま諦めて帰ってしまうはずの顧客をECサイト経由の注文に誘導できれば、貴重な購買熱を逃さず売り上げに繋げられます。
4.2.顧客満足度の向上に繋がる
顧客が望んだタイミング、望んだ形で商品を手に入れやすくなるオムニチャネルは、満足度向上の施策としても有効です。
品切れにより購買できない体験は、単に売り上げを逃すのみならず、自社に対するネガティブなイメージを抱かせます
一方、「○○(自社)ならいつでも買える」という安心感は顧客のリピーター化に好影響を与えます。
4.3.顧客データの分析が可能になる
オムニチャネル化を進めるなかでは、在庫情報や顧客データを一元的に収集・分析できる仕組みづくりも進めることになります。
チャネルを横断して顧客行動を可視化できるようになれば、「ECサイトでは購買率の低い顧客だが、実はサイトを確認後に実店舗で購買している」といった情報も得られます。
マーケティング施策の最適化はもちろん、自社の商品提供プロセスにおけるムダを省き、業務の効率化を進めることにも繋がるでしょう。
5.オムニチャネルを導入する際のポイントや注意点
一方、オムニチャネルの導入時には、大きく以下の4つのポイントを押さえておく必要があります。
5.1.長期的な目線で見る必要がある
オムニチャネルは成果が出るまでに時間がかかりやすい手法です。チャネルの統合的な連携を成功させたうえで、そこから相乗効果を生み出す施策を考えていく必要があります。
まずは一年間、取り組みを進めてみるなど、腰を据えた動きが不可欠です。
5.2.体制の整備や意識改革が大事
オムニチャネルの価値は接点同士の連携にあり、社内体制の整備や社員の意識改革も求められます。
SNS担当班とECサイト班で軋轢があるなどの理由でスムーズに連携ができない場合、オムニチャネルの意義は失われてしまいます。
5.3.ブランドイメージの統一が大切
オムニチャネルでは、接点を問わず顧客に同一の世界観を伝えることが大切です。チャネルごとのブランドイメージに違いがあると、顧客の混乱や離脱の原因となります。
特に、高級路線なのに特定のチャネルではいわゆる「安っぽい」施策を連発している、といったケースはロイヤルカスタマーの離反にも繋がり得るため注意が必要です。
5.4.セキュリティ対策も重要
全チャネルのデータを一元的に管理するオムニチャネルでは、仕組み上、情報漏洩時の被害が大きくなりやすい性質を持ちます。
業務レベルのセキュリティソフトを導入する、不要なアクセス権限を与えないなど、社内におけるセキュリティ体制の構築は必須です。
6.オムニチャネル化を進めるための手順
上記で解説したポイントを押さえたうえで、オムニチャネルを進める手順を確認していきましょう。
6.1.ロードマップを作成する
長期的な取り組みとなるオムニチャネルでは、最初に今後の指針となるロードマップを作成しておくことが大切です。少なくとも以下のポイントを意識して、ゴールまでの道筋を描いていきましょう。
- 現在保有しているチャネル
- 購買機会を喪失していると想定される箇所
(例:実店舗の在庫切れ、ECサイトにおける配送日数の長さ)
- 必要な対策
(例:店舗とECの在庫を一元管理、店頭在庫を用いた店舗受け取りの実施、近隣店舗からの配送など)
- 短期・中期・長期の目標設定
- 各取り組みの担当者・部門の明確化
6.2.カスタマージャーニーマップを作成する
続いて、企業視点で作成したロードマップに問題がないか、カスタマージャーニーマップの作成を通じて顧客視点でのチェックを行います。
カスタマージャーニーマップとは、顧客と自社製品の出会いから購買までを旅になぞらえて可視化するものです。
その有用性や作り方は以下の記事をご確認ください。
>>カスタマージャーニーとは?作成するメリットやマップの作り方・注意点を紹介
>>カスタマージャーニー作成におけるペルソナ設定の方法やポイント・注意点とは
6.3.チャネル間の連携強化や情報の一元化を進める
カスタマージャーニーマップの作成によりロードマップに問題がないと判断できたら、次は設定した取り組みを具体的に進めていきます。
ITツールを導入して顧客データや在庫情報の一元管理を進めるなど、チャネル間の連携を強化しましょう。
6.4.効果検証を行い改善策を検討・実行する
施策の実行後は、ロードマップで設定した目標を参考に効果の検証と改善を行います。重要となるのは、以下に代表されるKPIを定めておくことです。
- リピート購入率
- BOPIS(オンライン購入→店頭受け取り)の利用率
- 顧客満足度
- チャネル別の売上数値、比率
など
KPIを参考に達成・未達を判断していくと、次なる一手も見つけやすくなります。例えば、BOPISの利用率が低いならば、仕組みの周知は十分か、近隣店舗と在庫は適切に表示されているか、利用までの手順が面倒ではないか、といったポイントで改善策を検討していけます。
7.オムニチャネルを導入するならBrazeの活用がおすすめ
オムニチャネルの実現には、複数の顧客接点を統合的に管理できるツールの導入が不可欠です。その具体的な手段として、ぜひBrazeの活用をご検討ください。
顧客エンゲージメントプラットフォームの「Braze」は、アプリ、メール、SMS、ECサイトといったチャネルを横断したマーケティング施策の実行をサポートします。Brazeのプラットフォーム上で各チャネルの顧客情報を一元管理できるのはもちろん、メッセージの作成、送信、成果の測定までをまとめて作業できます。
多くのアクションがドラッグ&ドロップのような簡単な操作に対応しており、プログラムの知見がない方でも利用しやすい点も大きな特徴です。
自社単独での取り組みが難しい場合は、ぜひBrazeへのお問い合わせをご検討ください。
8.まとめ
オムニチャネルとは複数の顧客接点を連携させる手法であり、販売機会の損失防止や顧客満足度の向上に有効です。
オムニチャネルにはメリットがある一方、導入する前に注意すべきポイントもあります。まずは社内体制の整備や意識改革、セキュリティ体制の構築を進め、長期的な目線で考えていきましょう。
実践に際しては、自社の現状に適した施策を検討し、適切なITツールを導入していく必要があります。
Be Absolutely Engaging.™
Brazeの最新情報を定期的にお届け