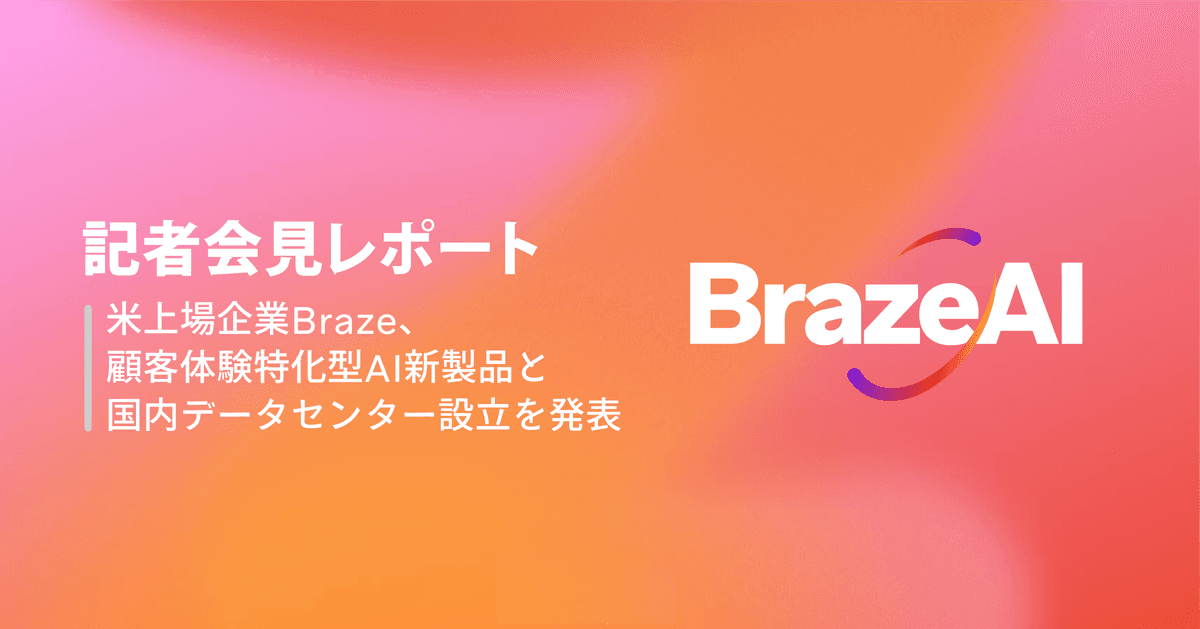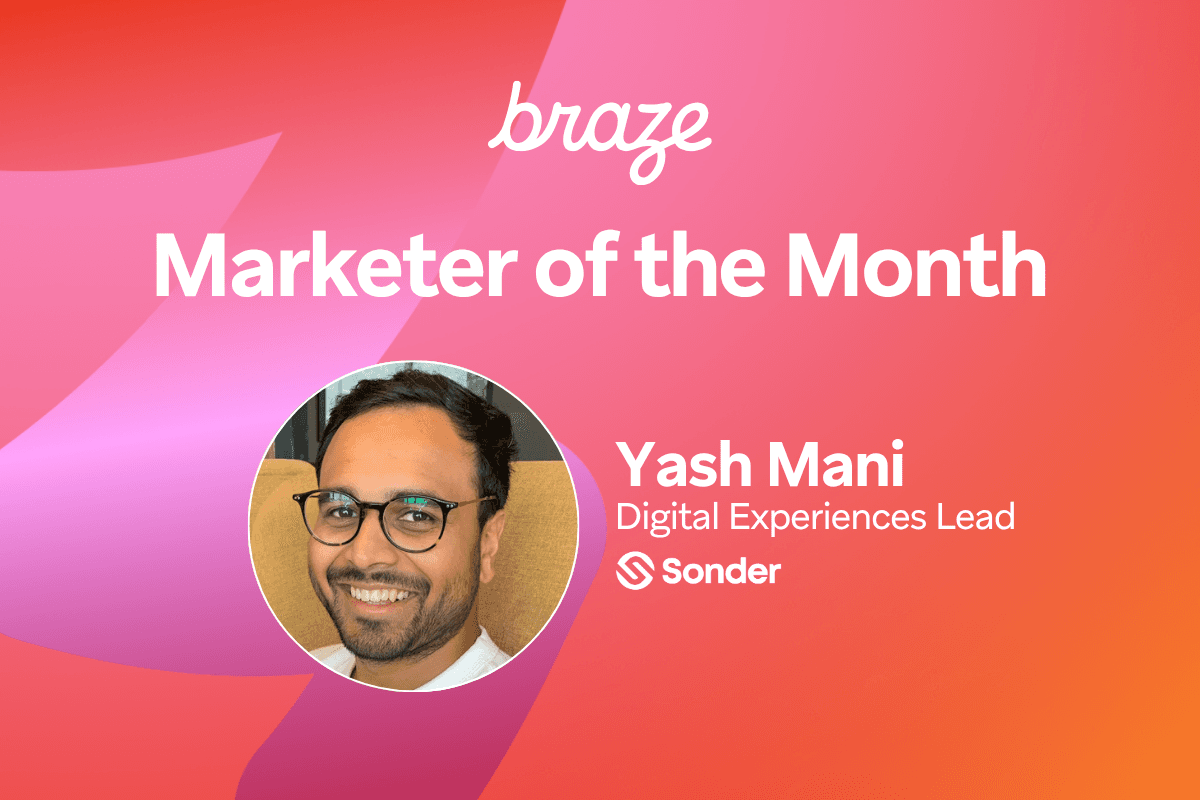生成AIを活用して業務効率化につなげる!活用事例や導入ポイントを紹介
公開 2025年9月17日/更新 2025年9月17日/13 分で確認


Team Braze
「業務の効率化には生成AIが有効」とする声を聞く機会が増えたと感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、具体的なイメージがつかめていない方も少なくないと思います。
この記事では生成AIについて、業務の効率化に必要とされる理由や得意な作業、注意点や成功事例、導入に向けてのポイントをご紹介します。
1.業務の効率化はなぜ必要?
生成AIの話を進める前に、そもそも業務の効率化はなぜ自社に必要なのか、簡単におさらいしておきましょう。
1.1.DXの推進が求められているため
多くの企業にとって推進が急務とされるDX(デジタルトランスフォーメーション)では、AIなどのIT技術の活用により自社のビジネスモデルさえ変えてしまうような変革が理想とされています。業務の効率化は、このような大規模な取り組みの一番の成果となります。
1.2.人材不足の対策・コスト削減のため
労働人口の減少や採用難は、業界を問わず深刻な課題となっています。限られた人員で最大限の成果を出すためには、効率化によって業務の無駄を省き、貴重な人的リソースを有効活用する必要があります。
また、単純作業や定型作業の自動化を進め、社員がより付加価値の高い仕事に注力できる環境を作り上げることも重要です。
1.3.業務の属人化を防ぐため
業務の属人化とは、「マクロを触れるのはAさんだけ」など、ある作業を特定の人材に依存している状態を指します。担当者の休退職により仕事がストップする可能性のある危険な状況です。
通常、業務効率化の過程では、特定の担当者が持つ知見やノウハウをITツールに保管するなど、情報の可視化を進めます。その取り組みが属人化の防止に繋がります。
1.4.競争力の維持や向上に必要なため
高速化する市場や顧客ニーズの変化に対応し、競争力を維持・確保するための手段の一つとしても、業務効率化は必要不可欠です。自社が効率化を怠り、他社が取り組みを進めれば、その差は顧客からの評価の差として遠からず返ってくるでしょう。
2.業務の効率化の実現には生成AIの活用が重要
このような背景のなか、業務の効率化を実現する手段として重要視されているのが、生成AIです。
生成AIは幅広い作業を得意としています。書類を紙からデジタルにするといった一部のプロセスだけ改善するのではなく、まるで高度な人材を新たに雇用したかのように業務全般で活用できます。
加えて、生成AIは疲れを知らず、人間のような調子の波もありません。DXが掲げる全社的な改革を現実のものとするための強力なパートナーとして活用が進んでいます。
3.従来のAIと生成AIの違い
昨今話題の生成AIと従来のAIには、以下のような違いがあります。
【従来のAI】
主に定型作業の自動化を担う
例:事前に与えた明確な条件のもと、画像の分類を行うなど
【生成AI】
新たなコンテンツを生み出すことができる
例:「ある商品のキャッチコピーを考えて」といった曖昧な指示にも対応できる
両者の違いや活用のメリット・デメリットは、以下の記事をご覧ください。
>>生成AI(ジェネレーティブAI)とは?AIとの違いや特徴、活用メリットについて解説
>>AIを導入・活用するメリット・デメリットとは?注意点や事例についても紹介
4.生成AIが得意な業務

では、生成AIはどのような業務を得意としているのか見ていきましょう。
4.1.データの調査・分析・予測
生成AIは、従来のITツールとは比べものにならないほど膨大なデータを取扱えるのが特徴です。
過去の広告施策のデータをまとめて分析し、担当者が気づいていないインサイトを導き出すなど、マーケターに新たな知見を与えてくれます。
4.2.コンテンツの生成
生成AIは、指示に合わせて画像や文章を作成してくれます。「この商品のキャッチコピーを考えて」「(与えた商品情報から)パッケージの画像を検討してみて」「広告のデータをわかりやすいグラフにして」と、担当者にお願いするイメージで作業を任せられます。
4.3.テキストの要約や作成・翻訳
手元にあるテキストの要約や翻訳は、生成AIが特に得意とする作業です。長時間におよんだ会議の議事録から重要箇所を要約したり、外国語の資料を高精度に翻訳したりできます。
難解な英語のレポートを「中学生でも理解できる日本語で」とお願いするなど、翻訳レベルを変えられるのも強みです。
4.4.アイデアを出す
顧客へ届けるコンテンツの準備や新たな宣伝施策の検討は、マーケターにとって終わりのない業務です。その点、疲労を感じない生成AIはアイデア出しの壁打ち相手として適しており、新奇性のある案の作成にひと役買ってくれます。
「メールのタイトル案を100個考えてみて」というような、人間には頼みづらい仕事も実行できます。
4.5.問い合わせ対応
近年は生成AIをお問い合わせ窓口として活用する例も増えています。24時間365日活動するAIチャットボットを初期窓口として配置し、人間の対応が必要な相談のみをカスタマーセンターが受け付けるようにすれば、顧客満足度の向上と人的コストの削減を同時に目指せます。
4.6.プログラムの生成や開発
生成AIは、プログラミングコードを記述したり、既存のプログラムの問題点を指摘したりする能力を持っています。
生成内容の真偽をIT人材がチェックする必要はありますが、プログラムの開発や改修にかかる工数を大きく削減できます。
4.7.スケジュール・プロジェクト管理
意外な活用法として、スケジュール・プロジェクト管理を生成AIで支援することも可能です。メールや社内チャットからタスクを抽出して半自動的にスケジュールへ入れたり(例:日時と場所付きで会議予定をカレンダーアプリに登録)、プロジェクトの進捗状況を与えて取り組みの成否を予測させたりと、有能な秘書を雇ったかのように活用できます。
5.生成AIを業務の効率化で活用する際の注意点
一方で、生成AIには以下のような注意点も存在します。
5.1.情報を取扱う際のセキュリティ対策が必要
ChatGPTをはじめとする主流な生成AIは、クラウドサービスとしてオンラインで利用する形が基本となります。
自社のオフライン環境で利用するツールと異なり、オンライン上で作業をしている=情報流出のリスクがあると理解しておかなければなりません。
社外秘の情報を与えない、定期的に対話内容を消去するなど、セキュリティ対策は必須です。
5.2.すべての情報が正しいとは限らない
生成AIはもっともらしい口調で誤った情報を提供することがあります。この現象はハルシネーションと呼ばれています。
取引先へ提供する資料の作成など、ミスが許されない作業の場合、出力内容は必ず人の目で確認をしましょう。
5.3.権利侵害や倫理的な課題がある
通常の生成AIは、その仕組み上、多くの著作物を学習して作られています。そのため、他者が権利を持つ著作物に類似するコンテンツを生成してしまうことがあるほか、「権利者の努力にフリーライドしているのではないか?」と倫理的な問題も指摘されています。
活用に際しては、誰かを傷つける形になっていないか、常に配慮を行うことが大切です。
5.4.AIに頼りすぎることによるヒューマンエラー
生成AIはきわめて便利な一方、頼り切りにすると社員の判断力やスキルを失わせてしまう恐れもあります。
AIは人が使いこなすべきツールです。「生成AIが出力したから」といった論拠を許さず、最終的な意思決定や作業の品質担保は人の手で行う風潮を社内に作り上げていきましょう。
5.5.AI人材の採用や育成が必要となる
自社に適した形でカスタマイズするなど、生成AIの本格的な活用を進める際にはAI人材の確保も重要となります。
しかし、AI人材の価値は高騰しており、外部からの採用は簡単ではありません。長期的な視野で研修体制を整えていくなど、社内で育成していくのも一つの方法です。
6.生成AIを実際に活用した事例
続いて、生成AIで業務の効率化に成功した事例をご紹介します。
6.1.事例1
ある大手コンビニチェーンでは、新商品の開発に生成AIの活用を進めています。全店舗の販売情報やSNS上のユーザーの声をデータとして収集・分析。このデータから生成AIに新商品のアイデア(画像や商品説明)を考案させています。
商品企画に必要な期間を最大で十分の一にまで削減できると期待されているそうです。
6.2.事例2
不動産関連事業を主に取扱うある企業では、生成AIがなければ実現できなかったであろうユニークなSNSキャンペーンを実施しました。
このキャンペーンは、あるタレントの画像を生成AIで1万種類も作成し、X(旧Twitter)のアカウントをフォロー&投稿をリツイートしてくれた方にランダムで一枚プレゼントするものです。そのインパクトから、SNS上で大きな話題を呼びました。
6.3.事例3
システム開発を手がけるある大手企業では、ChatGPTをベースとした自社向けのAIアシスタントサービスを開発しました。
国内の全社員約1万2,400人に利用を促し、検索エンジン代わりのような軽度の使用も含めて社内での活用を進めた結果、1年間で合計18.6万時間もの労働時間を削減することに成功しました。
7.生成AIを導入するためのポイント
最後に、注意点や事例を踏まえたうえで生成AIを導入するためのポイントをご紹介します。
7.1.課題を洗い出し・導入目的を明確にする
幅広い作業を得意とする生成AIの導入に際しては、どのように活用を進めるべきかを明確化しておくことが大切です。
業務の効率化を、といった曖昧な状態で導入しては、社内での利用も浸透しづらくなります。経営層から現場レベルまで聞き込みを進めるなど、現在の自社の課題を洗い出し、生成AIに何を担わせるべきなのか検討しておきましょう。
7.2.人材の確保や運用体制を整える
生成AIは、「○○をして」などと指示するだけで簡単に利用できます。しかし、事例でご紹介した通り、自社向けにカスタマイズすることができれば、より高度な業務効率化も実現できます。必要に応じてAI人材の確保を進めましょう。
また、権利侵害や情報漏洩などの各種リスクを抑えるためには、AI運用ルールやガイドラインの構築、社内への周知も重要となります。
7.3.必要な機能が備わったツールを選定する
生成AIは広汎な作業に対応していますが、ツールごとに得意とする分野は変わります。
創造性のある文章の作成を得意とするものや、マーケティング用の画像生成に強みを持つものなど、特徴はさまざまです。自社に適したツールを吟味しましょう。
8.まとめ
生成AIは、ほかのツールとは比較にならないほどの業務効率化を実現できる可能性を秘めています。一方、活用に際しては、ここでご紹介したような注意点を押さえておくことも大切です。
Brazeでは、「BrazeAI™」としてマーケター向けのアシスタント機能を提供しています。AIに自社のブランドイメージに適した文章や画像を作成させたり、顧客行動を高精度に予測して成果が期待できる一手を提案させたりなど、日々の業務の負担を軽減できる機能です。詳細は以下のページよりご確認ください。
Be Absolutely Engaging.™
Brazeの最新情報を定期的にお届け