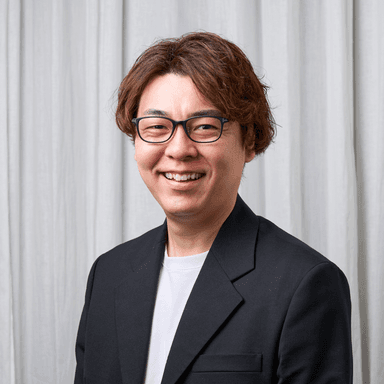SMSマーケティングの効果やメリットとは?活用例や成功するためのポイントを紹介
公開 2025年9月19日/更新 2025年9月19日/11 分で確認
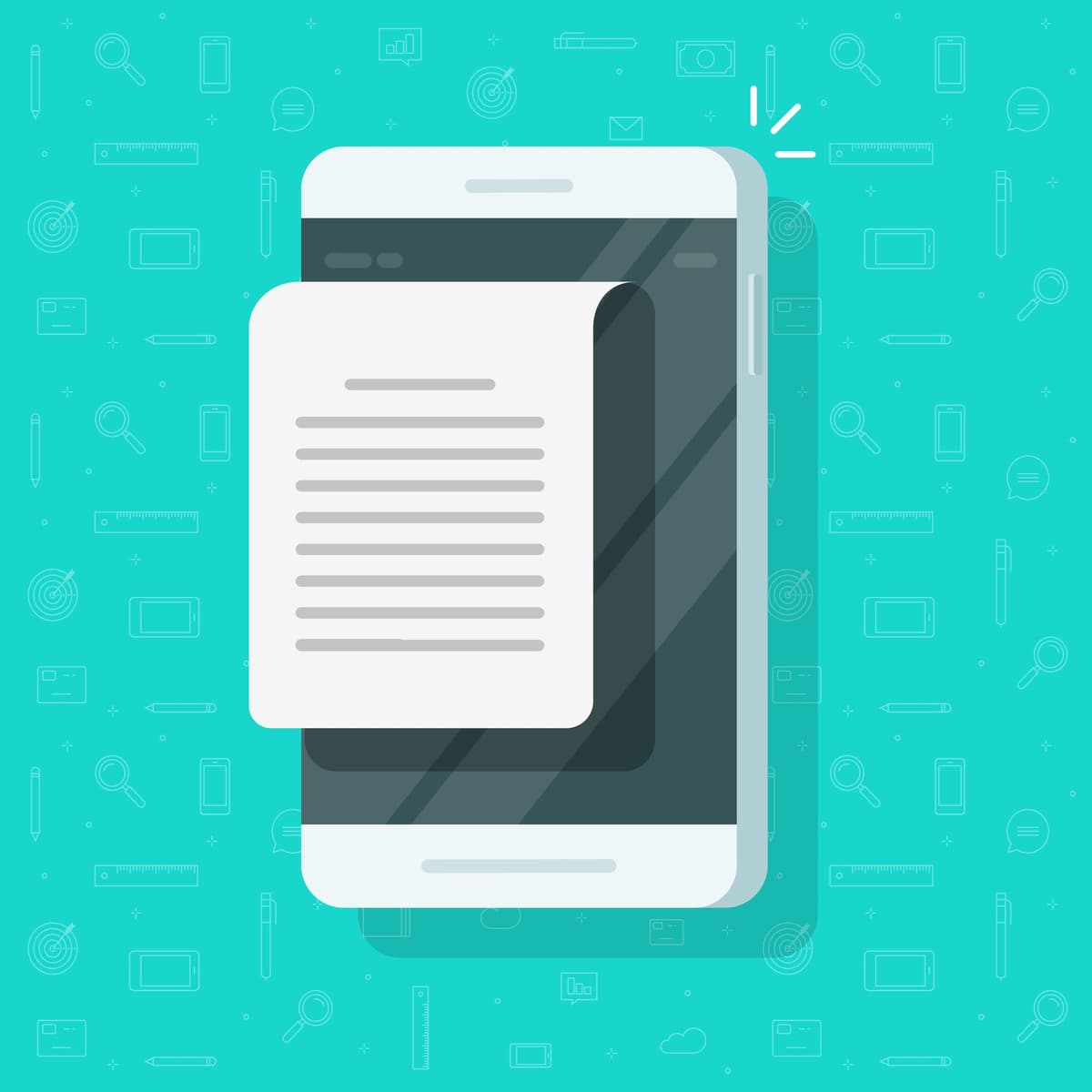

Team Braze
顧客へのメッセージの開封率や未達率に悩んでいるなら、SMS(ショートメッセージサービス)の利用がその有効な解決策になるかもしれません。
この記事では、SMSマーケティングについて、その特徴やメリット、注意点、活用例や成功のためのポイント、実践に役立つITツールなどをご紹介します。
1.SMSマーケティングとは
SMSマーケティングとは、携帯電話番号をもとにメッセージを送信するSMS(ショートメッセージサービス)を利用したマーケティング手法のことです。
大手通信会社の技術資料によれば、SMSはもともとモバイルコンピューティング(ノートパソコンや携帯電話などを外出先でも利用すること)を普及させるために登場しました。携帯一つで文字によるコミュニケーションが取れる画期的な手段という位置づけでした。
しかし、スマートフォンや携帯電話が圧倒的な普及を果たした今、SMSは企業からの重要なアプローチ方法の一つとして注目されています。
2.SMSマーケティングのメリット
SMSマーケティングには、ほかの連絡手段とは異なる独自の魅力があります。
2.1.到達率や開封率が高い
SMSは到達率も開封率も優れた連絡手段です。携帯電話番号に送信する仕組みのため、メールアドレスなどと比較して顧客が宛先を変更する頻度が少なく、長期にわたって関係を維持できます。
開封率は約98%にも及ぶとされており、一般的なメルマガ(同20~30%程度)と比較しても驚異的な数値です。
2.2.内容が伝わりやすい
SMSには文字数制限があり、メッセージが自然と短文になります。必要な内容だけを厳選して送信するため情報が伝わりやすく、顧客が長文を読み解いて自身の望む情報を見つけ出すような負担を削減できます。
2.3.幅広くアプローチができる
顧客の年齢や属性を問わずアプローチしやすい点もSMSの長所です。総務省の「令和6年版情報通信白書」によれば、2023年時点のモバイル通信機器の世帯保有率は約97.4%(スマートフォンは90.6%)とされており、SNSアカウントやメールアドレスを持たない層にも届けやすい傾向にあります。
2.4.費用対効果が高い
通常、SMSマーケティングでは法人向けの配信サービスを利用しますが、提供先によっては送信数が多くなるほど単価が下がるプランが用意されています。
一通当たり数円~十数円程度に収まるケースが多く、ハガキDMや電話営業などの連絡手段と比べてコストを下げられる可能性があります。開封率の高さから成果に結び付きやすい点も注目です。
3.SMSマーケティングを進める際の注意点
ご紹介したように、SMSマーケティングには開封率の高さやメッセージの伝わりやすさなどの魅力がありますが、一方で注意点も存在します。
3.1.文字数の制限がある
SMSには文字数制限があります。当初は全角文字で最大70文字となっていましたが、現在では最大で670文字までとなっており、670文字に対応していない機種の場合は、70文字ごとに分割して表示されます。
また、文字以外の画像や動画の送信にも対応していません。ただし、URLの送信は可能であるため、リンク先を通じて画像や動画を届けることはできます。
3.2.プライバシーへの配慮が必要になる
SMSは特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)の対象となりうる連絡手段であり、顧客のプライバシーへの配慮を怠った場合、法律に抵触してしまう可能性があります。
代表的な違反例は以下の4つです。
- 原則としてあらかじめ送信の同意を得た者以外の者への送信の禁止
- 一定の事項に関する表示義務(例:送信者や苦情の受付先など)
- 送信者情報を偽った送信の禁止
- 送信を拒否した者への送信の禁止
出典:迷惑メール相談センター「特定電子メール法 | 迷惑メール対策」
実務では、事前に送信の同意を得るオプトインと、顧客が送信を拒否できるオプトアウトの仕組みが重要となります。詳細は後述します。
3.3.費用が高くなる可能性がある
前述の通り、SMSは優れた費用対効果を見せる可能性を秘めたマーケティング手段です。しかし、従量課金制のプランが多いため、送信数が増えるごとに費用もかさみやすい傾向にあります。
総額でどの程度のコストがかかるのか、コンバージョンの期待できる送信内容かといったポイントは事前に確認しておきたいところです。
4.SMSマーケティングの活用例を紹介

続いて、SMSをマーケティングに活用する例をご紹介します。
4.1.セールやキャンペーン・イベントのお知らせ
セールやキャンペーンのお知らせなど、周知したい情報を伝えることは、SMSの定番の活用方法です。連絡を即時に届けられ、開封率も高いSMSは、「本日限定タイムセール」のような即時性の高い宣伝にも向いています。
4.2.利用や来店を促すためのクーポンの配布
「再来店で試供品をプレゼント!」「ふたたびのご購入でお支払い料金を20%OFF」など、クーポンを配布する手段としてもSMSは適しています。
位置情報との組み合わせにより、実店舗の近くを通りかかった顧客に割引クーポンをプレゼントする、といったユニークな施策も実現可能です。
4.3.お客様アンケートの依頼
SMSにURLを記載すれば、お客様アンケートの依頼を届けることも可能です。開封率の高さから、ほかの手段よりも多くの顧客にアンケート実施中であることを伝えられるでしょう。
4.4.来店客へのフォローアップ
SMSは、「昨日はご来店いただき誠にありがとうございました。もしお気づきの点がありましたら~」などフォローアップをする手段としても重宝します。
到達率と開封率の高さから顧客へメッセージが届きやすく、顧客を自社に引き留めやすくなります。
4.5.予約情報のリマインド
ほかにも、SMSの開封率の高さを活かす例として、予約情報のリマインドがあります。「明後日の○○時にご来店をお待ちしております」とメッセージを用意し、万が一の予約キャンセルの場合に連絡できるURLも記載しておけば、店舗にとってダメージの大きい当日キャンセルや予約放置を削減できます。
4.6.本人確認
即時に連絡を届けられるSMSは、本人確認の手段としても有効です。近ごろは、銀行やWebサービスの二段階認証の方法としてSMSが利用されている例もよく見かけます。登録済みの電話番号に認証用の数列が届き、その入力を通じて本人確認を行う形が代表的です。
5.SMSマーケティングを成功させるには
ご紹介したメリットや注意点、活用例を押さえたうえで、SMSマーケティングを成功させるためのポイントを見ていきましょう。
5.1.興味を持ってもらえるような内容を考えることが重要
SMSマーケティングは、限られた文字数のなかでいかに顧客の興味を引きつけられるかが成否を左右します。
もちろん、顧客の興味を引く内容の用意は難しく、マーケターの永遠の課題ではありますが、一つの手がかりとなるのがパーソナライズの考え方です。
顧客を属性や行動履歴などのデータから細分化し、各グループの顧客ニーズを満たせる内容を届けられれば、すべての顧客に画一的な内容のSMSを送る場合よりも反応は良くなるはずです。
5.2.オプトインの取得・オプトアウトの用意が必要
SMSの送信前には、前述のオプトイン(顧客からSMSの送信許可を得ること)、オプトアプト(顧客がSMSの送信許可をいつでも取り消せること)の準備も欠かせません。
オプトインは、商品の購入時やサービスの申し込み時に「携帯電話番号宛に広告や宣伝の連絡をしても良いか」と同意を得る形が主流です。一方、オプトアウトは、SMSの最下部などに「今後の送信を希望されない方はこちら」のようなURLを用意し、リンク先の自社サイト等で解除してもらうケースがよく見られます。
ただし、オプトイン、オプトアウトは法律が絡む問題です。自社が準備すべき具体的な形式は、法務部や外部の専門家にご相談ください。
5.3.送信する時間帯や頻度に気をつける
到達率と開封率の高いSMSは、配信の時間帯や頻度に細心の配慮が必要です。夜間や早朝に届いたり、何度も繰り返し連絡がきたりしては、自社に対する反感に繋がります。
「月に数回、昼休憩や退勤直後を狙って送信する」など、実際の開封率やコンバージョン率も見ながら、自社に最適な形を探っていきましょう。
5.4.ツールを活用する
セグメント化、送信時間帯や頻度の模索など、SMSマーケティングではデータ活用が重要な場面が多くあります。分析機能を持つITツールの導入が成功への近道です。
例えば、顧客エンゲージメントプラットフォーム「Braze」では、適切な顧客に適切なタイミングでSMSを送信するための機能を提供しています。
事前に用意した顧客データや実際の送信結果を分析し、「この行動をした方にこのSMSを送信する」とトリガーを設定して、半自動的なSMSマーケティングを実現できます。
詳細は以下のページをご覧ください。
5.5.定期的に見直し改善を繰り返す
SMSマーケティングは一度はじめてしまえば安心というわけではなく、PDCAサイクルを回すことが重要な取り組みとなります。
顧客ニーズと自社の想定にズレが生じた場合、開封率が高い長所がそのままネガティブな反応を生みやすい短所として返ってきます。コンバージョン率やオプトアウト数を常に計測し、取り組みのブラッシュアップを続けていきましょう。
6.まとめ
ショートメッセージサービスを利用し効果的な宣伝を実現するSMSマーケティングでは、実践前に文字数制限や法的規制などの注意点を押さえておく必要があります。注意点を押さえ、PDCAを回しながら適切な施策を実行できれば、高い成果を自社にもたらしてくれる可能性を秘めています。
自社に適したSMSマーケティングの形を検討し、より高い効果を求める場合は、ぜひBrazeのご活用もご検討ください。
Be Absolutely Engaging.™
Brazeの最新情報を定期的にお届け