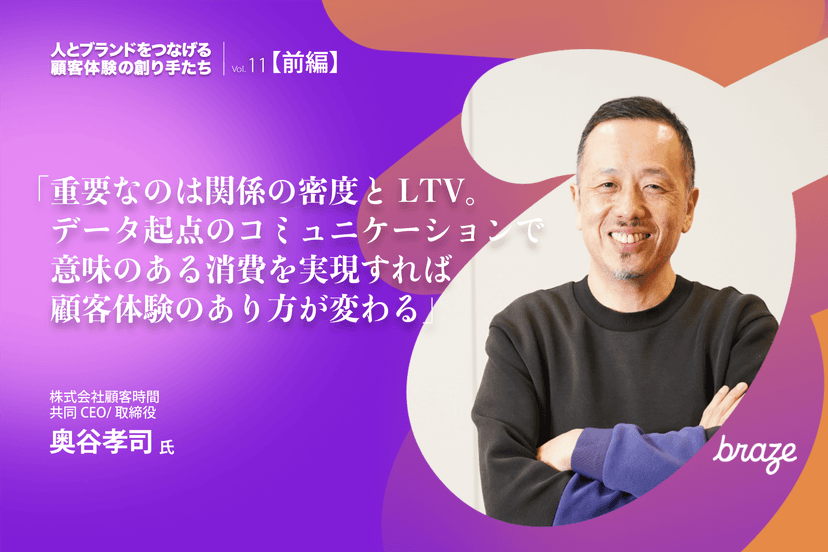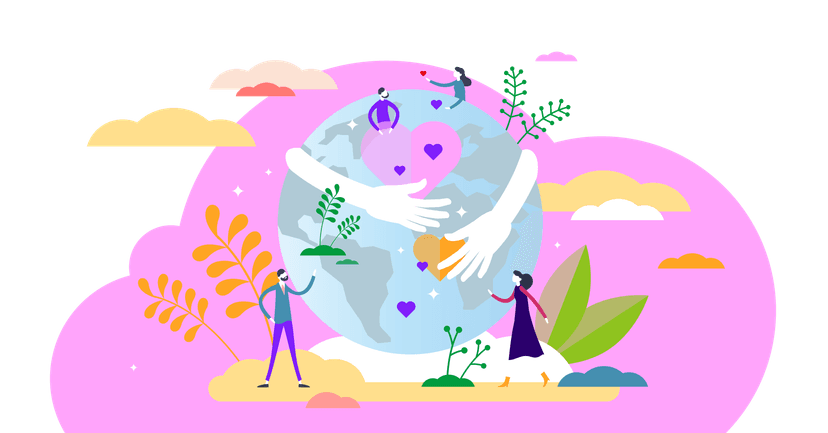人とブランドをつなげる 顧客体験の創り手たち Vol.10 | 石戸亮さん
公開 2025年11月19日/更新 2025年11月19日/11 分で確認
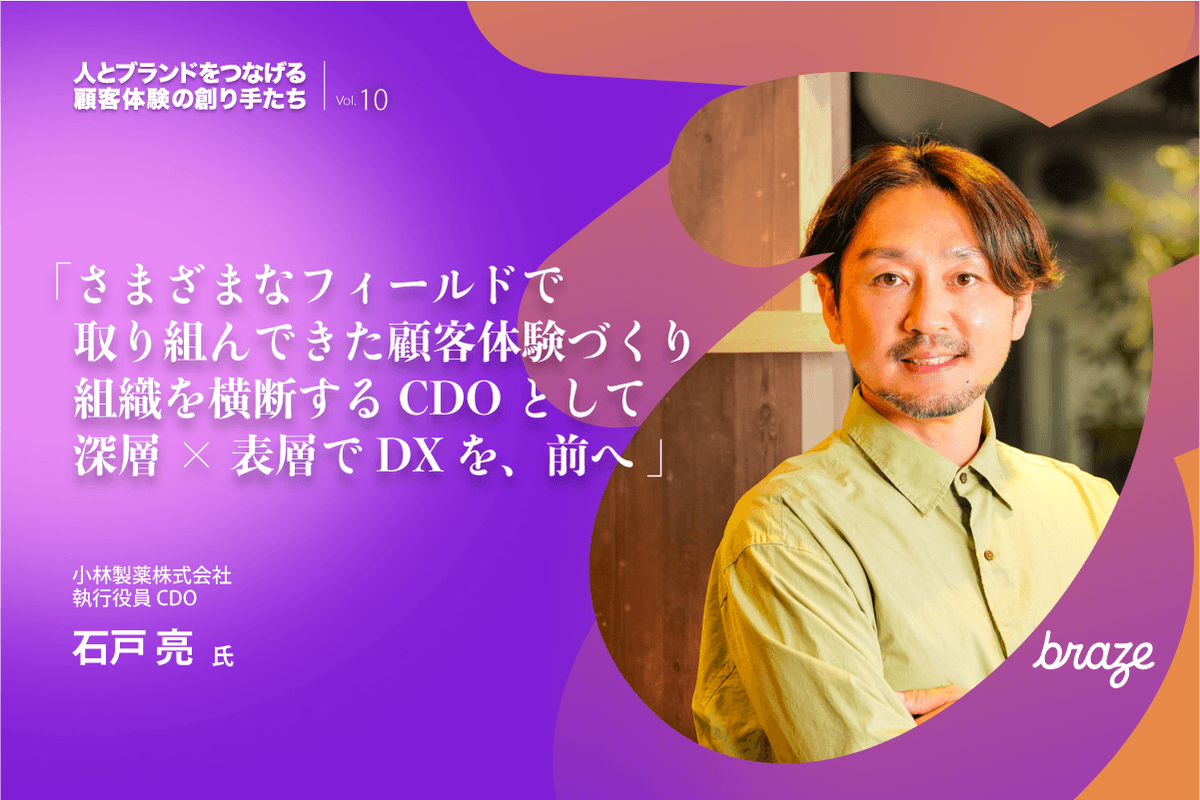

Team Braze
人とブランドの“つながり”をつくる、挑戦者たちの物語
Brazeでは、顧客とのエンゲージメントに革新をもたらす人々に独自でインタビューを行い、彼らの挑戦と成果を紹介する「人とブランドをつなげる 顧客体験の創り手たち」をお届けしています。現場での知見や工夫、Brazeの活用方法など、実践的でリアルなストーリーを通じて、マーケティングの未来を考えるヒントを共有していきます。今回は、小林製薬株式会社 執行役員 CDO 石戸亮さんにお話を伺いました。
顧客体験づくりの経験値を高めたキャリア序盤
-ベンチャー、外資系、国内メーカーや老舗企業など、石戸さんのキャリアパスは多彩ですが、キャリアのスタート時点で明確なプランはあったのでしょうか。
石戸 キャリアの原点となると大学時代にさかのぼり、友人たちと始めたフリーペーパー事業になります。運営資金獲得のために広告営業を行いながら、「出稿してもらうには魅力的なコンテンツが必要だ」と気づき、クリエイティブにも力を入れ、自分たちなりに真剣に取り組んでいました。就活せず、「このまま会社を立ち上げる」と意気込んでいたものの、理工学部だったこともあり、経営のことはさっぱり分かっていませんでした。紙の媒体に限界を感じて行き詰まり感もあった頃、「サイバーエージェントの藤田晋社長が(当時)最年少で東証マザーズに上場」というニュースにふれたんです。10歳年上で、すごい人がいると思ったのが強く印象に残っています。

-これからはインターネット広告の時代だと共感できる部分があったと?
石戸 そうですね。フリーペーパーの事業を行いながら漠然と感じてはいたものの、具体的にどう動けばいいのかまでは考えが至っていませんでした。サイバーエージェントはそれを形にしていましたし、様々なことを経験できるのではと思い入社することに。最初は何年か勉強したら起業しようと考えていました。
-広告営業から始めて後に子会社の立ち上げも担当されています。ある程度やり切り、次のキャリアステージとしてGoogleへ、というところでしょうか。
石戸 海外でチャレンジしたい思いがあり、サイバーエージェントにもその可能性のあるソリューションはあったのですが、当時の会社の事業計画と私の考えをうまく重ね合わせることができなかったので、転職する覚悟を決めました。Googleを選んだのは、英語をものにしたかったのと海外でビジネスを進めるネットワークをつくるためです。その経験を持って、「次は海外拠点のある日本企業で働きたい」と思い、様々な企業と話しをすすめていましたが、何か決め手に欠けていました。そんな中、イスラエル発のAIスタートアップ企業からお声が掛かって転職し、その企業の日本進出に携わり、M&Aの流れでSalesforceに在籍することに。これまでのキャリアの前半は、明確なビジョンというより経験値を高めることを優先していた気がします。
CDOは組織を横断する翻訳者、越境者
テックジャイアントと呼ばれる企業を経て、2020年から日本のメーカー、パイオニアでCDOを務めていますが、ここがキャリアの大きな転換点に感じます。
石戸 ずっと広告営業、マーケティングなど事業を支援する側だったので、事業を行う側での経験値を高めたいという思いがありました。でも、それ以上に人材の流動化に対して大きな違和感を抱きました。当時、私が在籍していた企業も含めテックジャイアントが採用を大幅に強化し、IT業界に多くの人材が流入しましたが、メーカーをはじめ日本企業から見ればデジタル人材の流出です。その結果、せっかく導入したシステムを本来の価値通りに使いこなせない状況に陥っていました。逆に考えると、デジタル化によるインパクトが大きいのは日本の大手メーカーや中小企業であり、そこにこそ自分の経験を生かせるのではないかと考え、CDOをお引き受けいたしました。

- 石戸さんが考えるCDOの役割について聞かせてください。
石戸 情報システム、デジタルマーケティング、データ関連、DXなど、企業によって立ち位置は変わり、日本の場合は会社に合わせてCDO自身が定義しなくてはならないところがあると感じます。私の場合、経営と現場とデジタル、その間に立って組織をつなぐブリッジといいますか、翻訳者、越境者的な立ち位置でしょうか。歴史、伝統ある企業の場合、現在と未来、そして過去をつなぐという役割もCDOには求められると思います。
- 2023年には小林製薬のCDOに就任しています。一般消費財の会社で、例えば顧客体験づくりという視点で今までとは別の苦労もあるのでしょうか。
石戸 2021年からデジタル戦略アドバイザーとして携わり、業務理解、課題に対する解像度は上がっていると感じていました。入口はデジタルやDXであっても、本質的な経営課題はどの企業にも相通じるものだと思い、自分の経験、バリューで貢献できるという手応えもあったので、要請をお受けすることにいたしました。
-小林製薬が抱えていた課題とは?
石戸 市場で評価されている商品という資産があり、従業員は熱意も意欲も旺盛で、アイデアがどんどん湧いてくる企業風土もありました。そうしたアセットを、デジタルを使ってどう成長に反映させていくか、というのが1つ。また、それこそ頭からつま先までをケアする商品があり、商品の数だけ顧客とのタッチポイントが存在しています。ただ、個々の商品でコミュニケーションを深めるのは難しく、自社ECの運営もドラッグストアとの関係など考慮しなくてはならない部分があります。商品を使うという体験を起点に、顧客エンゲージメントを高める方法には様々な考え方、やり方があるはずですが、ここは今も試行錯誤を重ねているところです。これは小林製薬に限らず、一般消費財メーカーにとって共通の課題ではないでしょうか。
深層を根気よくほぐすことで表層の変化が加速する
-顧客エンゲージメントを考えるポイントとして「深層のDX、表層のDX(CX)の組み合わせ」があります。石戸さんはこの「深層のDX、表層のDX(CX)」について、どう考えているのでしょうか。
石戸 表層はCX、顧客満足度としてわかりやすいのですが、深層に関して、私はBX、EXという視点で見ています。CXにつながるマーケティング、セールス系の領域では、最先端のテクノロジーがどんどん生まれていますし、爆発的な変化を生む環境が整っています。ただ、上から号令をかけて最新ツールを導入したとしても、業務フローを変えるのが意外に難しく、使うための仕事が増えてしまうような場面がよくあります。場合によっては、過去の仕事のやり方を否定しなければならない部分もあり、特に歴史ある企業ほど、資産や思いと成果の間にギャップが生まれるのかもしれません。

-石戸さん自身、そういう現場をたくさん見てきたと?
石戸 過去のやり方も10年前、20前にそれを導入したときには善意で実行され、一定の成果をあげてきたはずです。それがデジタル、データの時代にそぐわなくなり、刷新が求められたとき、「刷新すべきだ」と思う反面、人を含めて過去の善意を否定することをためらう心理が働いても不思議ではありません。そこで意味を持つのが深層のDX、私が言うところのBX、EXで、突き詰めると人や企業の風土であり、そう簡単には変わらないものです。ですが、根気強く向き合い、ほぐし、変化対応力を高める必要があります。深層をほぐすことで表層の取り組みが加速すれば、結果的に顧客体験が向上していくはずで、2つは両輪の関係にあるのではないでしょうか。
-深層をほぐすことで表層の変化を促すというのは面白い視点ですね。顧客体験の視点で、日本の企業はものづくりに強みがある反面、顧客接点力が不足しているという指摘もあります。テクノロジー活用を含め、顧客接点力を高めるためには何が必要でしょうか。
石戸 あくまでも個人的な印象ですが、日本企業の顧客接点力は高いと思います。地理的に見ても、東京から北海道、九州への移動には飛行機で2時間もかかりません。アメリカは国土が広く国内移動にかなりの時間を要すため、日本のように全国をカバーするマスメディアの概念がなく、州や地域ごとの独自性が強くなります。そのような環境だからこそ、マーケティングはアメリカで体系化され、空間を超えて運用できるデジタルソリューションが発展していったのだと思います。
Brazeのようなツール導入に現場を巻き込みたい
-日本は地理的に顧客接点を持ちやすい環境にあったため、デジタル化、DXに遅れてしまった、と。
石戸 逆説的に感じるかもしれませんが、そういう側面はあるでしょう。距離が近いと、顧客との関係づくりは属人化する傾向にあり、暗黙知化にもつながるからです。前述した深層の部分ですね。ここをほぐさずに、CRMツール、MAツールなどを導入してもうまく定着しない可能性は高くなります。Brazeのようなツールを導入する際、システムやデジタル関連の部署だけでなく、営業部門にも当事者として関わらせるべきではないでしょうか。属人化、暗黙知化する顧客との関係性をデータとして取り込み、共有知として集積することで、組織全体で顧客解像度を高められるはずです。その上で、コミュニケーションを深める施策を検討していけば、もっと高いレベルの顧客エンゲージメントを実現できると思いますし、私も実際に取り組んでいます。

-最後に、短期的に成し遂げたいこと。少し長い射程で取り組みたい目標など、これからのキャリアについて聞かせてください。
石戸 キャリアを通じて、例えばマーケティング、営業、データなど、1つの領域を突き詰めてきたわけではないため、そこに対して若干のコンプレックスはあります。一方、翻訳者、越境者的な立ち位置で、自分にしかできないことに取り組んで向き合ってきた、という自負もあります。短期的には、老舗企業のDX推進を中心に、翻訳者、越境者としての在り方、関わり方を追究したいですね。もう少し視点を先に向けると、デジタルやデータ活用を特別な手段としてとらえるのではなく、それがあってあたり前の経営を研磨し、体現していきたいと考えています。最終的には、CDOという言葉を使わなくても考え方や仕組みが自然にインストールされているような組織になるのが理想。そこで自分がどういう仕事をしているのかは……社会の動きを見ながら考えていこうと思います。
Be Absolutely Engaging.™
Brazeの最新情報を定期的にお届け