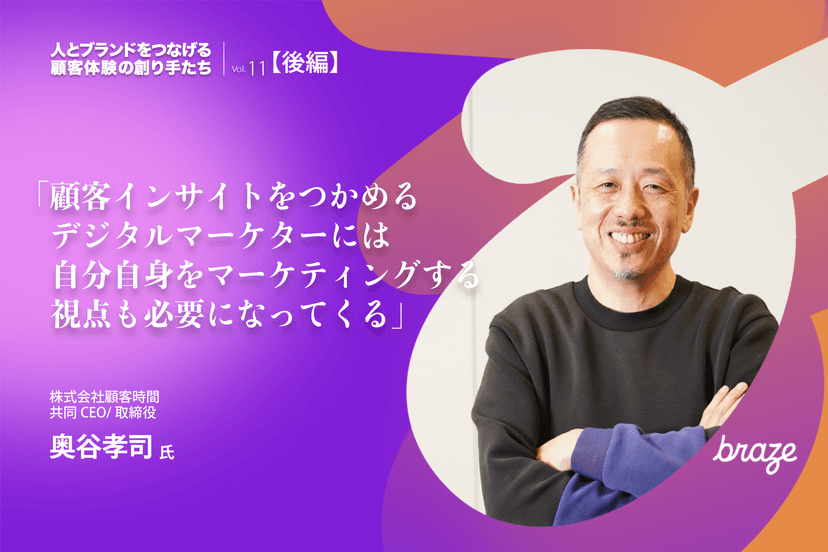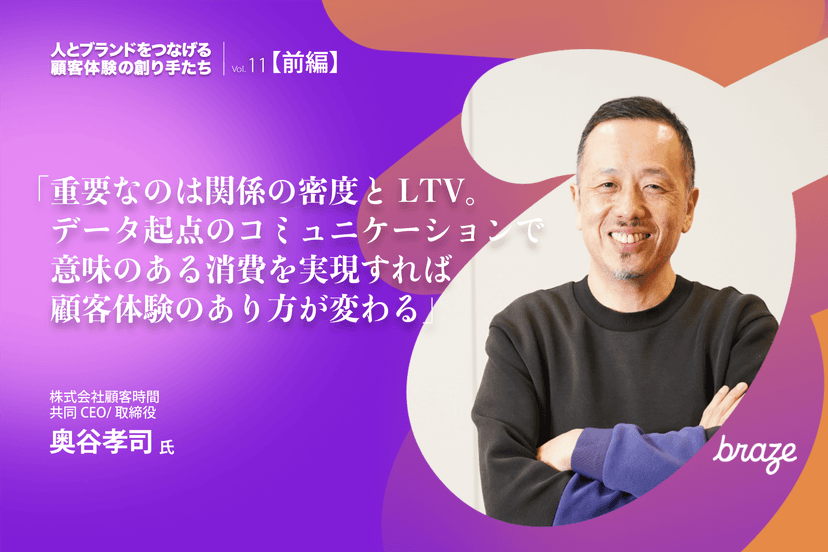セグメンテーションとは?分類方法や重要な要素、活用事例について解説
公開 2024年7月10日/更新 2024年7月11日/12 分で確認


Team Braze
どんなに優れた製品も、市場の選択を誤れば思うように売上を獲得できません。そうしたリスクを回避し、自社が狙うべき顧客層の明確化に役立つのが「セグメンテーション」です。
この記事では、セグメンテーションの定義や重視される理由、代表的な分類方法、意識すべき4つの要素、関連用語との違いや成功事例などをご紹介します。
1. セグメンテーションとは
セグメンテーション(Segmentation)とは、市場にいる顧客を属性・趣味嗜好・ニーズなどの切り口でグループ化し、自社のターゲット像を明確にするマーケティング作業です。日本語では「市場細分化」や「顧客層細分化」と訳されます。
セグメンテーションを理解するためには、その前提となる「セグメント」の意味を知る必要があります。
1. セグメントの意味
セグメント(Segment)は、名詞としては「区分」、動詞としては「分割する」などの意味を持つ英単語です。転じてマーケティング分野では、ある切り口によってグループ化された、同じ要素を持つ集団・顧客層を指します。
例えば、「関西エリアに住む30代女性」や「過去に自社のメルマガを申し込んだ男性」などの集団がセグメントとなります。
セグメントにおけるグループ分けの切り口はさまざまです。代表的な分類方法は後述します。
2. セグメンテーションの意味や定義
セグメンテーションを分かりやすく簡潔に表現するならば、似通った特徴を持つ複数のグループに顧客を分け、それぞれの特徴を理解したり集団別に最適なアプローチを考えたりすること、となります。
市場の顧客をセグメントに分け(セグメント化)分析を進める取り組みが、セグメンテーションと定義されます。
2. セグメンテーションはなぜ重要?
セグメンテーションはマーケティングの成功のために必須ともされ、顧客理解やパーソナライズされた施策の実現に役立ちます。その重要性を深掘りしていきましょう。
1. 情報収集チャネルの多様化
近年はSNSや動画サイトが人々に浸透し、消費者の情報収集チャネルが多様化しています。テレビCMのように企業側が能動的に発信する宣伝の場以外からも、人々が自由に情報を集められる時代です。しかし、企業からはその接点が見えにくい可能性もあります。
顧客をグループに分けて実態を深掘りしていくセグメンテーションは、自社が見落としているそうした顧客接点の把握を助けます。
2. ユーザーニーズの多様化
情報収集チャネルの多様化は、ユーザーニーズの多様化も生み出しました。日常的に触れる情報が一人ひとり異なるため、個人がそれぞれの課題や嗜好を持ちやすくなり、企業が顧客ニーズを満たす難易度は高まっています。
セグメンテーションによりニーズを把握することは、その難易度を下げ、質の高い顧客体験を提供するための第一歩となります。
3. マーケティング手法の変化
マーケティング手法の変化もセグメンテーションの重要性が指摘される理由です。
一昔前は、マーケティングといえばテレビCMなどの「マスマーケティング(不特定多数の大衆に同じ宣伝をする手法)」が当たり前でした。しかし、先ほどもご紹介した情報収集チャネルとユーザーニーズの多様化から、このような最大公約数的な手法だけでは成果は上がりにくくなっています。
より高い成果のためには、よりパーソナライズされた施策が求められており、セグメンテーションはそのための足掛かりとなります。
3. セグメントテーションの代表的な分類方法
セグメンテーションの代表的な分類方法(グループ分けの基準とする要素)には、次の4種類があります。
1. 行動変数(behavioral variables)
行動変数とは、過去の行動・態度・知識量などで顧客をグループ化するための変数です。以下が例として挙げられます。
【行動変数の例】
- 購買履歴やメルマガ登録の有無
- 利用状況(例:毎日使うヘビーユーザー、夏期シーズンのみ利用)
- 知識量(例:ヘビーユーザーで使いこなしている、興味はあるが利用経験はない)
- 返品・返金に関する態度
行動変数は、「夏期のみ使うユーザーに別の季節の魅力を紹介する」など、自社製品と顧客との関係において、現状に合わせたマーケティング施策を行う際に用いられます。
2. 人口動態変数(Demographic variables)
人口動態変数(デモグラフィック変数)とは、年齢や性別といった個人の客観的な属性をもとにした変数です。代表例には以下が挙げられます。
【人口動態変数の例】
- 年齢
- 性別
- 家族構成
- 職業
- 年収
- 学歴
人口動態変数の情報はアンケートなどで収集しやすく、また「子どもを持ち、将来のために収入を増やしたい年収○○○万円の30代の男性」などと明確なターゲット像の設定に役立つことから重宝されています。
3. 地理的変数(Geographic variables)
地理的変数(ジオグラフィック変数)とは、居住国や居住地域といった、文字通り地理的な要因による変数です。代表例には以下があります。
【地理的変数の例】
- 居住国や地域、市区町村
- 気候(例:降雪が多い、降雨量が少ない)
- 人口密度
- 交通インフラの充実度(例:公共交通機関が主な移動手段)
- 宗教的要因(例:特定の食べ物が禁止されている)
地理的変数は、新規出店先を吟味するなど、実店舗型のビジネスを成功させるためのセグメンテーション基準として用いられます。
4. 心理的変数(Psychographic variables)
心理的変数(サイコグラフィック変数)とは、ある人の価値観や信念、考え方や購買動機といった内面的な要素を指す変数です。例えば以下のようなものがあります。
【心理的変数の例】
- 無添加や無香料などのナチュラルな製品を好む
- 食品は大手メーカーの商品を積極的に選ぶ
- 品質よりも値段の安さを重視する
- 通信販売は実店舗と比べて信頼できないと思っている
- 友達と出かけるよりも自宅でひとり穏やかに過ごすのが好き
心理的変数は、ほかの変数は同じであるのに購買行動に差がある人々を、別々のグループとして取り扱う際に役立ちます。
例えば、「同じエリアに住む似た年齢・家族構成・収入の人々のなかに、近場のアパレル店を利用する人とまったく訪れない人がいる」といった場合には、通販への信頼性や価格と品質のどちらを重視するかなどによってセグメント化します。
4. セグメンテーションに必要な4つの要素

セグメンテーションを活用する際には、各セグメントの価値の見極めが大切な作業となります。見極めが間違っていると、注力すべきでない顧客層を自社のターゲットとしてしまうリスクがあるためです。
セグメントの検証では、これからご紹介する4Rの要素が有効となります。
1. Rank(顧客の優先順位)
Rankは、顧客層の優先順位、すなわちセグメントの優先順位を意味する視点です。「自社のビジネスモデルと関わりの深い顧客層か」「経営戦略上、優先したい相手なのか」といった観点での評価を指します。
2. Realistic / Realistic Scale(市場規模の有効性)
Realistic / Realistic Scaleは、収益に関する視点です。「そのセグメントから十分な収益を確保できる可能性はあるのか」など、市場規模の有効性を測ります。市場規模が十分でない場合、ほかの要素が満たされていたとしてもビジネスとしての成功は困難です。
3. Reach(到達可能性)
Reachは、「そのセグメントに対して自社が製品・サービスを届けることは可能か」を測る到達可能性の視点です。例えば、魅力的なマーケットであっても遠方にあるなど地理的要因から製品を届けられないのであれば、自社が狙うべき顧客層からは外れます。
4. Response(反応の測定可能性)
Responseは、顧客の反応を確認できるか、すなわち「施策の効果測定を行えるのか」の観点です。Responseが不足していると取り組みの成否が把握できず、新たなマーケティング施策の検討が難しくなります。
そのほか、最近では、市場の将来性を測る「Rate of Growth(成長性)」、競合他社の強さを見る「Rival (競合情報・競合状況)」の2つを足して「6R」とされるケースもあります。いずれにしても重要なのは、多角的な視点からセグメントを評価することです。
5. 事業戦略やマーケティング戦略に必要な要素
ご紹介してきた通り、顧客を細分化して分析を進めるセグメンテーションは、顧客視点を踏まえた事業戦略やマーケティング戦略の検討に欠かせない作業です。
ここでは、セグメンテーションのほかに、事業戦略やマーケティング戦略に必要なフレームワークについて紹介します。
なお、セグメンテーションの先にある事業戦略の重要性やその作り方は、以下の記事で解説しています。
>>事業戦略の目的や重要性とは?戦略の立て方やフレームワーク、ポイントを紹介
1. フレームワーク「STP分析」
STP分析とは、マーケティング戦略立案の基礎となる「市場の把握」「ターゲットの選定」「自社の立ち位置の決定」を行うためのフレームワークです。マーケティングの神様とも称される米国の経営学者フィリップ・コトラー氏が提案したもので、以下の3つのステップに分かれています。
【STP分析のステップ】
1.セグメンテーション(Segmentation):市場の細分化・顧客のグループ化
2.ターゲティング(Targeting):自社が狙うべきセグメントの選定
3.ポジショニング(Positioning):競合を考慮した上での自社の立ち位置の決定
名前のSTPは、各工程の頭文字を表しています。セグメンテーションはSTP分析の最初のステップに当たり、その次のターゲティング、ポジショニングの前提と位置づけられます。
2. ターゲティング(Targeting)
ターゲティングとは、分類したセグメントのなかから自社が狙うべきものを決定する、セグメンテーションの次の作業のことです。
ただし、セグメンテーションとの境目は曖昧で、前述の4Rや6Rにおいてセグメントを評価する作業はターゲティングに含まれるものとする考え方もあります。
3. ポジショニング(Positioning)
ポジショニングとは、ターゲティングで選定した市場の競合調査を進め、自社のスタンスを定めることです。競合と比較した強み・弱みを分析し、自社が狙うべき立ち位置を決定します。分析すべき項目は多岐に渡りますが、少なくとも以下は押さえておきましょう。
【ポジショニングで競合と比較すべき要素】
- 価格
- 機能面
- 実績
- 市場への製品の供給可能数
- 利用可能な販売チャネルの種類
- 潜在的顧客(固定ファン)の数
- 「自社ならではの価値」の有無
6. セグメンテーション戦略の活用事例
最後に、Brazeを活用してセグメンテーション戦略に挑戦した、アフリカのビデオストリーミングサービス「Showmax社」の事例をご紹介します。
同社では事業戦略として、「無料体験後の有料会員登録数の増加」「サービスのリテンション率(顧客維持率)の上昇」「解約ユーザーの復帰の促進」の3つの目標を掲げていました。しかしながら、各目標の対象となるユーザーは「無料体験中の方」「契約中の方」「解約済みの方」とそれぞれ状況が異なります。
そこで、Brazeを用いた顧客のセグメント化を実施。契約状況やコンテンツの視聴時間などからユーザーを細分化し、それぞれに適切なメッセージを送信しました。結果として、有料会員の加入者数が204%にまで増加し、リテンション率も71%と高水準に維持するなど、サービスの改善に成功しています。
>>加入者数を204%増加させた Showmax社のセグメンテーション戦略
7. まとめ
セグメンテーションとは、市場にいる顧客をさまざまな切り口で細分化し、グループ別の特徴を分析していく作業です。顧客ニーズを踏まえたマーケティング戦略の立案に欠かせない過程となります。
Brazeでは、人口動態変数や行動変数などの多様な分類方法で、顧客を柔軟にセグメント化できる機能を提供しています。また、「セグメントインサイト」と呼ばれる仕組みにより、セグメント別のKPIや行動結果の計測も容易です。
自社が狙うべき顧客層の分析に関する相談は、以下のリンクよりお進みください。
Brazeセグメントインサイトについて詳しくはこちらもご覧ください。
>>Brazeのデータ視覚化機能で顧客エンゲージメントの現状を明確に把握する
関連タグ
Be Absolutely Engaging.™
Brazeの最新情報を定期的にお届け